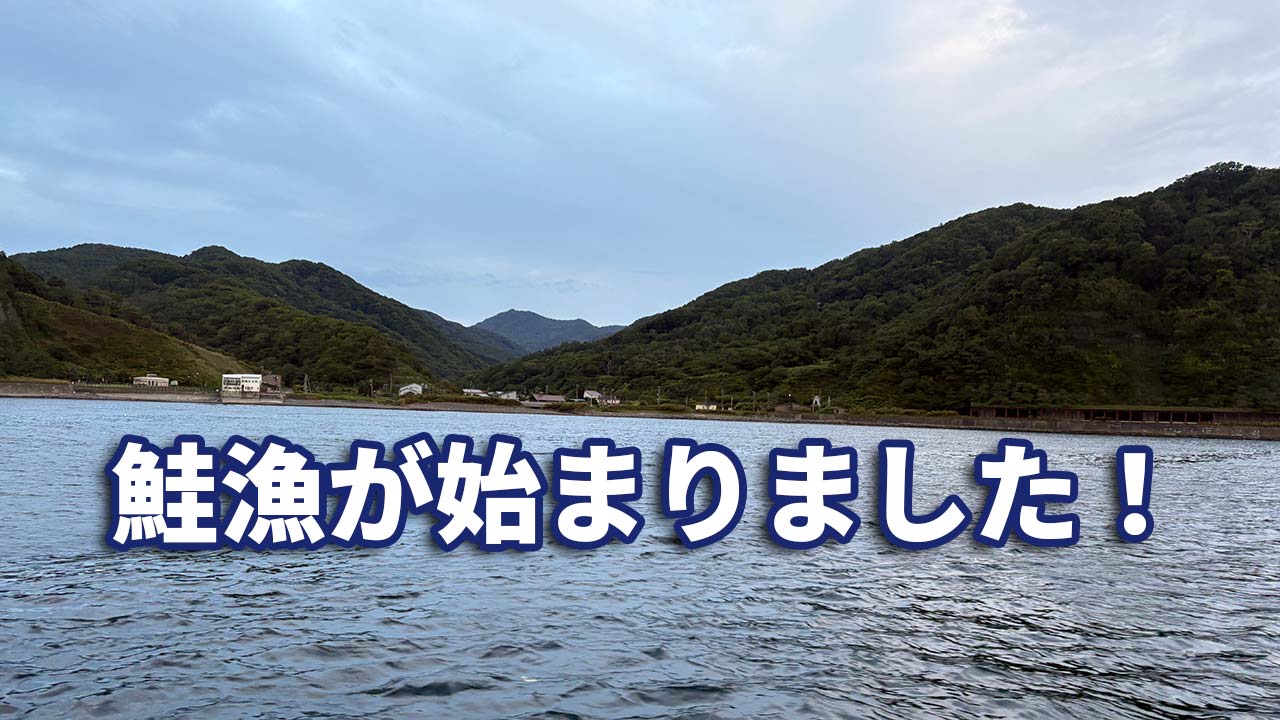はじめに本日より鮭の定置網漁がはじまりました。序盤なのでまだまだ量は少ないですが、これから本格的にはじまります。予想では不漁という報道がありますが、こればっかりはわかりません期待しかありません!
このブログの最後に珍しいものが網にかかってましたよ。
釣り人の間でよく話題になるテーマのひとつが、「鮭やサクラマスはリーダーを見抜いて嫌うのに、青や緑のルアーにはよく反応する」という現象です。
一見すると矛盾しているように思えますが、魚の視覚特性や行動学を踏まえると、実は非常に理にかなったものなのです。
この記事では、鮭とサクラマスに限定し、彼らの線視力、定置網の垣網との関係、さらには「遡上期には餌を食べないのになぜルアーや餌にバイトするのか?」という疑問まで掘り下げて解説します。
1. 鮭とサクラマスは視覚に優れた魚
鮭やサクラマスは、魚類の中でも特に視覚が発達したグループに属します。
- 線視力が高い
魚の線視力とは、「どれだけ細い線を識別できるか」を示す能力です。サケ科は人間に換算して視力0.3〜0.6程度の線視力を持ち、細い糸や異物を見抜けると言われています。つまり、透明度の高い海や川ではリーダーを“線”として認識し、「これは不自然だ」と警戒する可能性が高いのです。 - 青緑に敏感
サケ科の網膜は青(450nm前後)〜緑(500〜550nm)の波長に特に強く反応します。これは、海中で赤い光が減衰し、青や緑が残りやすい環境で生きてきたための適応です。ベイトであるイワシやワカサギ、オキアミの体色とも一致しており、青緑は「餌の色」として強くインプットされています。
2. ラインはなぜ嫌われるのか?
自然界には「一直線のもの」がほとんど存在しません。木の枝も海藻も岩の割れ目も、必ず曲がりや揺らぎがあります。
しかし、釣り糸は水中でピンと張られ、直線的に伸びています。これこそが魚にとって不自然な存在なのです。
- 不自然な直線=自然界にない異物
- ルアーに付随する線=捕食対象ではない信号
特に鮭やサクラマスのように線視力が高い魚は、こうした「線」を見抜きやすく、違和感を覚えるとバイトせずに反転してしまう。サクラマスキャスティングで「追ってきたのに食わない」現象は、まさにこの典型例です。
3. 青緑ルアーが効く理由
一方で、鮭やサクラマスは青や緑のルアーに好反応を示します。これには明確な理由があります。
(1) ベイトの色に近い
イワシやワカサギの背中は青緑色を帯びています。鮭やサクラマスにとって、青緑は「日常的に見ている餌の色」であり、違和感がないのです。
(2) 環境光と一致する
海の中で残るのは青と緑の光。さらに植物プランクトンが発生すると海は緑がかって見えます。そんな環境下で青緑ルアーは自然に溶け込み、魚に「本物のベイト」と錯覚させやすいのです。
(3) 動きが際立つ
背景に溶け込む色だからこそ、ルアーの「動きの変化」だけが強調されます。動体視力に優れたサケ科は、この“動きの違和感”に反応して追尾・バイトするのです。
4. 垣網に学ぶ「線」の力
鮭漁で使われる定置網には「垣網(かきあみ)」という部分があります。
- 岸から沖に向かって伸びる長大な網の“壁”
- 鮭が回遊してきてこの線にぶつかると、反転せずに沖へ沿って泳ぐ
- そのまま「囲い網」→「落とし網」に誘導されて漁獲される
魚はまっすぐ進む習性があり、障害物に当たると本能的に「沖へ逃げる」行動を取ります。
これは「線=障害物」として強く認識している証拠であり、リーダーを嫌う理由と非常によく似ています。
- ライン:不自然な線 → 避ける・警戒する
- 垣網:強力な線 → 沿って泳ぎ、結果的に捕獲される
どちらも「線が行動を左右する」という点で共通しており、鮭の行動原理を理解するうえで欠かせないヒントになります。
5. 遡上期に餌を食べないのになぜバイトするのか?
一般的に「遡上した鮭は捕食しない」と言われます。確かに川に入ると消化器官が退化し、栄養を取るための捕食はほとんど行いません。
ではなぜ、ルアーや餌に口を使うのでしょうか?
(1) 縄張り意識・攻撃行動
産卵期の鮭はテリトリー意識が強くなり、侵入者を追い払うために攻撃行動を取ります。ルアーやタコベイトは「餌」ではなく「侵入者」として噛みつかれている可能性が高いのです。
(2) 捕食本能の残存
稚魚の頃から「動くものに口を使う」習性が身についています。成魚になってもこの反射的行動は消えず、ルアーの動きに思わず口を使ってしまうのです。
(3) 匂いや味の刺激
鮭は嗅覚が極めて発達しています。釣り人が実践する「にんにく」「味の素(グルタミン酸)」「サンマやカツオの切り身」「バナエエビを赤く染める」などは、すべて嗅覚や色覚を刺激し、攻撃性を高める要素になります。
(4) 色刺激
赤は婚姻色や血の色に通じ、鮭にとって「ライバルの色」。赤く染めた餌が効くのは、捕食ではなく「攻撃のスイッチ」を押している可能性があります。
6. 実釣に生かす工夫
(1) リーダー対策
- 細めのフロロ(16〜20lb程度)で「線の存在感」を消す
- 長さは極端に長くせず、ルアー周りの違和感を減らす
(2) ルアーカラー戦略
- 澄み潮:ブルーバック、グリーンシルバー
- プランクトン豊富:グリーンゴールド、チャート系
- 攻撃性刺激:赤やオレンジをアクセントに
(3) 餌釣りの工夫
- 匂いを強める(にんにく、グルタミン酸)
- 色で刺激する(食紅で赤くする)
- 油分のある餌(サンマ、カツオ)は強力な嗅覚刺激になる
まとめ|相反するけど理にかなっている
- 鮭やサクラマスは線視力が高く、リーダーを「不自然な線」として見抜き、警戒する。
- 一方で青緑ルアーは「自然界のベイト色+環境光と一致」するため、安心して追いかけ、動きに反応してバイトする。
- 遡上期に捕食しないのに口を使うのは、縄張り意識・反射的行動・匂いや色刺激による攻撃反応が理由。
- 定置網の垣網が魚の行動を「線」でコントロールするように、リーダーやルアーの線や色も魚の行動を左右している。
つまり、リーダーは違和感を与え、ルアーは自然に見える。食わせるのではなく怒らせる。
この相反する要素を理解することで、鮭やサクラマス釣りは一層奥深くなるのです。
本日早朝に網にかかったのは、アオリイカの胴長35cmくらいでした。北海道もこのサイズが釣れるようになればいいですね。一匹いれば多数いるはずですからね。