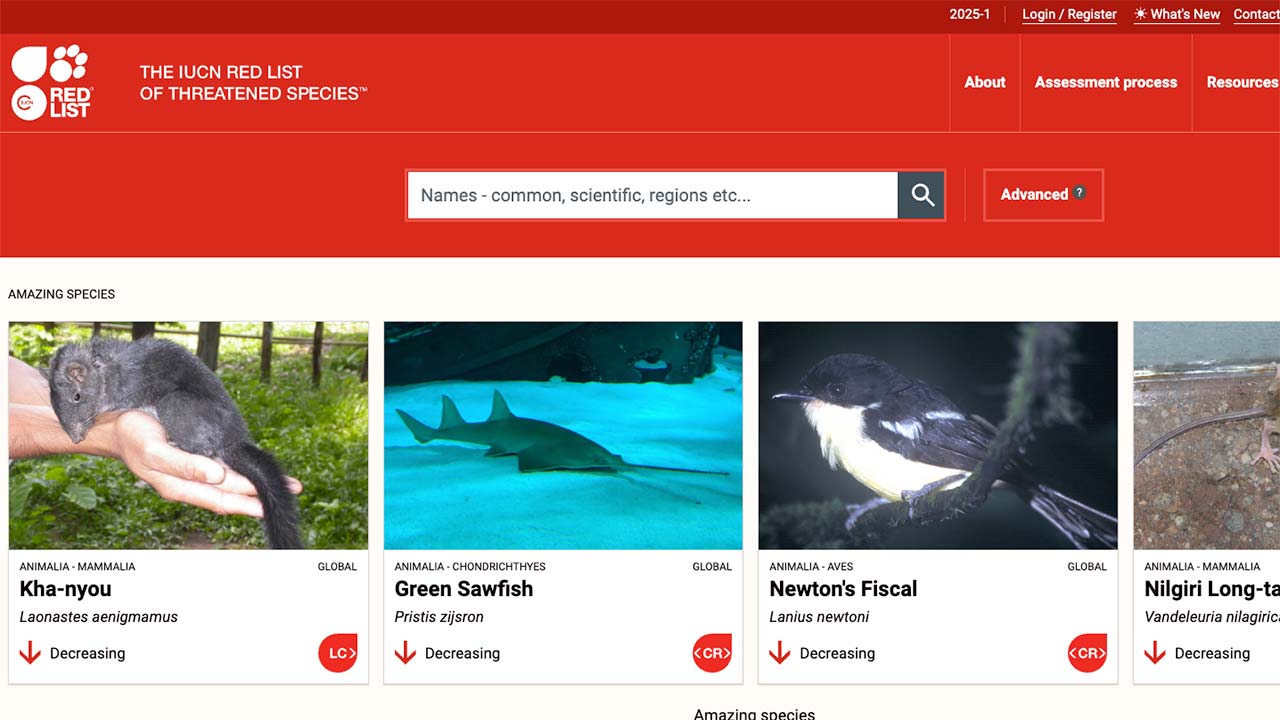◆ 世界で最も高価な魚「クロマグロ」
クロマグロ――その名を聞いてまず思い浮かべるのは、築地や豊洲での初競り、超高級寿司ネタとしての「大トロ」ではないでしょうか。
世界的にも「黒いダイヤ」と呼ばれるほどの高値が付き、日本をはじめアメリカ・中国などで高い需要を誇る魚です。
ところが、そんなクロマグロが2014年、絶滅危惧種に指定されるという衝撃的な出来事がありました。なぜ、海の王者がそんな事態に追い込まれたのでしょうか?
◆ 絶滅危惧に陥った理由
- 乱獲の常態化
クロマグロは成長が遅く、成熟するのに5年以上かかるため、持続的に獲るには慎重な管理が必要。ところが、30kg未満の若魚(ヨコワ)が大量に漁獲される事態が常態化。 - 特に日本では、刺身文化による強い需要があり、幼魚の段階で獲ってしまう漁業が続けられてきました。
- 産卵場の特定と集中漁業
クロマグロは主にフィリピン海(日本近海)やメキシコ湾で産卵します。
産卵場が特定されると、繁殖期に集中して漁獲されるというリスクが発生。卵を産む前に成魚を獲る行為は、資源再生産を著しく妨げます。
- 管理の遅れと分断
日本を含む西太平洋の漁業国では、個別の利害関係や政治的事情から、なかなか厳しい漁獲制限が導入されませんでした。
国際的な合意(WCPFC、IATTC)もなかなかまとまらず、結果として「獲った者勝ち」の漁業が長く続いたのです。
「獲った者勝ち」の漁業は個人経営が主流のため、資源管理が困難という問題
沿岸漁業の大多数は家業・小規模経営で、全体最適よりも個人利益の最大化が優先されがちです。
その結果、「今獲らなければ他の誰かが獲る」という心理(※レース・トゥ・ザ・ボトム)に陥り、獲り尽くしが加速します。
◆ IUCNが「絶滅危惧種」に指定(2014年)
2014年、ついにIUCN(国際自然保護連合)が、太平洋クロマグロ(Thunnus orientalis)を「絶滅危惧II類(Endangered)」に指定しました。
● IUCN(国際自然保護連合)の根拠
親魚(30kg以上)の資源量が過去最大水準のわずか2.6%まで減少。
若魚が育つ前に大量に漁獲され、産卵親魚が激減。「このままでは回復不能なレベルに陥る」と判断されたのです。
◆ それからどうなったのか? 〜回復の兆し〜
- 2015年、日本が本格的に漁獲枠制度(TAC)を導入
日本国内では、30kg未満と30kg以上で漁獲枠を分ける管理が始まり、違反時には漁獲停止などの措置も。 - WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)やISCなどの国際機関が厳格な資源管理を開始
資源評価の精度が上がり、「20年で回復させる計画」が策定された。
日本、台湾、韓国、メキシコ、米国などが参加。
- 資源は着実に回復傾向へ
2022年時点で、親魚資源量は約4.8万トンに回復。
歴史的最低水準から約2倍に増加。国際資源評価では、短期的回復目標をすでに達成。
しかし、課題も残る。 IUCNの評価はまだ変わらず、2021年のレッドリスト改訂で、太平洋クロマグロは「準絶滅危惧」に変更されました。
● 密漁・違法操業・監視体制の脆弱さ
一部では、割り当て以上の漁獲や、報告義務のない漁獲が問題視されています。特に日本沿岸では、遊漁の釣り人の影響なども指摘されつつあります。
遊漁クロマグロ違反行為
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/2005458
漁師の闇クロマグロ
https://www.fnn.jp/articles/-/857198
判決「懲役3カ月、執行猶予2年の有罪判決」となった
クロマグロの遊漁に対しては、様々な意見があります。まず規制を30kg以下にするべきだという意見は、国際ルールで決定しているために変更はまずありえません。
現在の遊漁の枠が年間60トンという数字は、資源が回復するともっと大きくなる可能性は高いと思われますので、まだ我慢の時期であると思います。もちろんこの数字は決して高い数字とは言えません。
まずは、資源の回復を待つ以外にありません。2015年に始まった漁獲枠制度(TAC)は20年計画で進められています。今年でちょうど10年経過し、回復傾向になっているので今は我慢の時期とも言えます。
着実に大型化してきていますし、今の制度で行くのが今のところベストだと思います。
ですが、釣りということを考えると「キャッチアンドリリース」を推奨していくべきたと思っています。スポーツフィッシングが盛んな外国の例を紹介します。
【クロマグロのキャッチアンドリリース(C&R)に関する国際事例】
◆ 1. アメリカ合衆国(東海岸・メキシコ湾)
・対象魚種:アトランティック・ブルーフィン・ツナ
・制度化:NOAA(米国海洋大気庁)が科学的資源管理と連携
・主な特徴:
- キャッチ&タグ&リリース(T&R)方式を推進
- 釣果情報(サイズ・位置・時刻)をアングラーが報告
- スポーツフィッシング大会ではC&R部門を設置
・成果:
- マグロの回遊ルート・成長データが収集され、管理計画に活用
- 漁業とレジャーの両立による地域経済の活性化
◆ 2. カナダ(ノバスコシア州など)
・対象魚種:アトランティック・ブルーフィン・ツナ
・主な特徴:
- 世界的なクロマグロ釣り観光地
- 商業漁業とは別枠でリリース専用の観光ツアーを許可
- T&Rに対応する船長ライセンス制
・成果:
- 科学研究機関との協力により資源管理が高度化
- リリースされた魚の追跡データが豊富に蓄積
◆ 3. スペイン(地中海沿岸)
・対象魚種:アトランティック・ブルーフィン・ツナ
・制度化:EU漁業規制の枠組みの中で実施
・主な特徴:
- レクリエーショナルフィッシング枠の中でC&Rライセンスを導入
- 釣行ごとの事前登録、報告義務あり
- 地中海での産卵期に合わせて漁期やエリア制限も併用
◆ 4. イタリア・フランス
・対象魚種:アトランティック・ブルーフィン・ツナ
・主な特徴:
- タグ&リリース大会を開催
- NGOや地元大学との連携によるデータ共有
- 環境教育的要素も盛り込み、次世代アングラーへの啓発活動を展開
◆ 5. その他の国・地域
・オーストラリア:南半球における回遊型マグロの保全に向けたC&R実証試験を実施
・ニュージーランド:キングフィッシュなどで実績があり、マグロ類にもC&R適用可能性を検討中
◆ キャッチアンドリリースの効果
資源保護 : 親魚や若魚の再放流により資源再生産を促進
科学調査 : タグ情報により回遊ルート・成長速度・生残率などを把握
意識啓発 : 環境保護への理解促進、次世代アングラー教育
経済波及効果 : 釣りツーリズムの拡大による地域経済の活性化
◆ 日本は
現在、日本におけるクロマグロC&Rの法制度化は未整備だが、民間レベルでは自主的なリリースも一部実施されている
C&Rと連動した「釣り観光・エコ漁業」モデルの構築が期待される
IUCN(国際自然保護連合) https://www.iucn.jp/
WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)
IATTC(全米熱帯まぐろ類委員会)
【ノルウェー漁業の成功と日本への示唆】
ノルウェーは、世界的に見ても最も成功した「持続可能な漁業国家」の一つとされます。その背景には、科学に基づく厳格な漁獲枠管理制度(TAC)や、個別譲渡可能枠(ITQ)の導入といった高度な資源管理体制が存在します。本稿では、ノルウェー漁業の歩みと成果を紹介し、日本の沿岸漁業や資源管理に対する教訓を探ります。
◆ ノルウェー漁業制度の特徴
ITQ制度の導入
・1990年代に導入された「個別譲渡可能枠(ITQ)」により、漁業者一人ひとりに明確な漁獲枠が割り当てられる。
・枠は売買・譲渡が可能で、過剰な競争や過剰投資を防止。
・漁業者は「たくさん獲る」よりも「限られた枠内で高品質な魚を獲る」方向へシフト。
科学的TAC設定
・ノルウェー海洋研究所などが実施する資源評価に基づき、毎年魚種ごとのTAC(漁獲可能量)を決定。
・科学者・政府・漁業団体の三者協議により、政策的なバランスと透明性を確保。
リアルタイム監視とトレーサビリティ
・すべての漁船にGPSと電子ログブックを搭載。
・漁獲情報はリアルタイムで政府機関へ報告。
・水揚げ港での陸揚げチェックと、輸出までのトレーサビリティが制度化。
◆ 資源回復と経済効果
・乱獲で減少していたタラ資源が回復し、現在では世界最大規模の資源量を誇る。
・ニシンやサバなども安定供給が可能となり、輸出産業として大きな成長を遂げる。
・ITQにより漁業者は計画的に操業でき、魚価も安定。
・漁獲枠が資産化し、漁業者の所得は1.5〜2倍に向上したとされる。
◆ 制度導入時の反発と対応
・ITQ導入初期には、「枠を持たない漁師が排除される」「富が一部に集中する」などの反発が激しく、抗議活動も発生。
・しかし、政府は以下の対策で対応:
- 小規模漁業者用の地域枠を確保
- 若年層や新規参入者への支援制度を整備
- 一部の枠に譲渡制限を設け、地域外への流出を抑制
◆ 漁業者の意識と社会的評価
・「資源を守れば将来も漁業で食べていける」という意識が漁業者に浸透。
・漁業は国家資産であり、国民全体のものという社会的認識が形成。
・透明性と公平性の高い制度設計が、信頼を築いた。
◆ 日本への示唆
科学的根拠に基づくTACと資源評価の整備
- 日本でもクロマグロやサンマなどでTAC導入が進んでいるが、対象魚種の拡大と精緻な評価が必要。
地域小規模漁業への配慮
- ノルウェーのように、地域枠や新規参入支援を組み込むことで、持続性と公平性の両立が可能。
デジタル技術と監視の強化
- 日本の沿岸漁業でも、簡易なGPSやアプリ型日報などを活用したモニタリング体制が求められる。
社会的合意形成と漁業者との信頼構築
- 制度改革には時間と説明、漁業者との継続的な対話が必要。トップダウンでなく「共創」がカギ。
◆ おわりに
ノルウェー漁業の成功は、一朝一夕に成し遂げられたものではありません。制度への反発や混乱を乗り越え、科学・技術・合意形成の三本柱を長年積み上げた成果です。日本でも、資源の持続可能性と漁業者の生活を両立させる漁業モデルの再構築が求められています。その際、ノルウェーの事例は大きなヒントとなるでしょう。