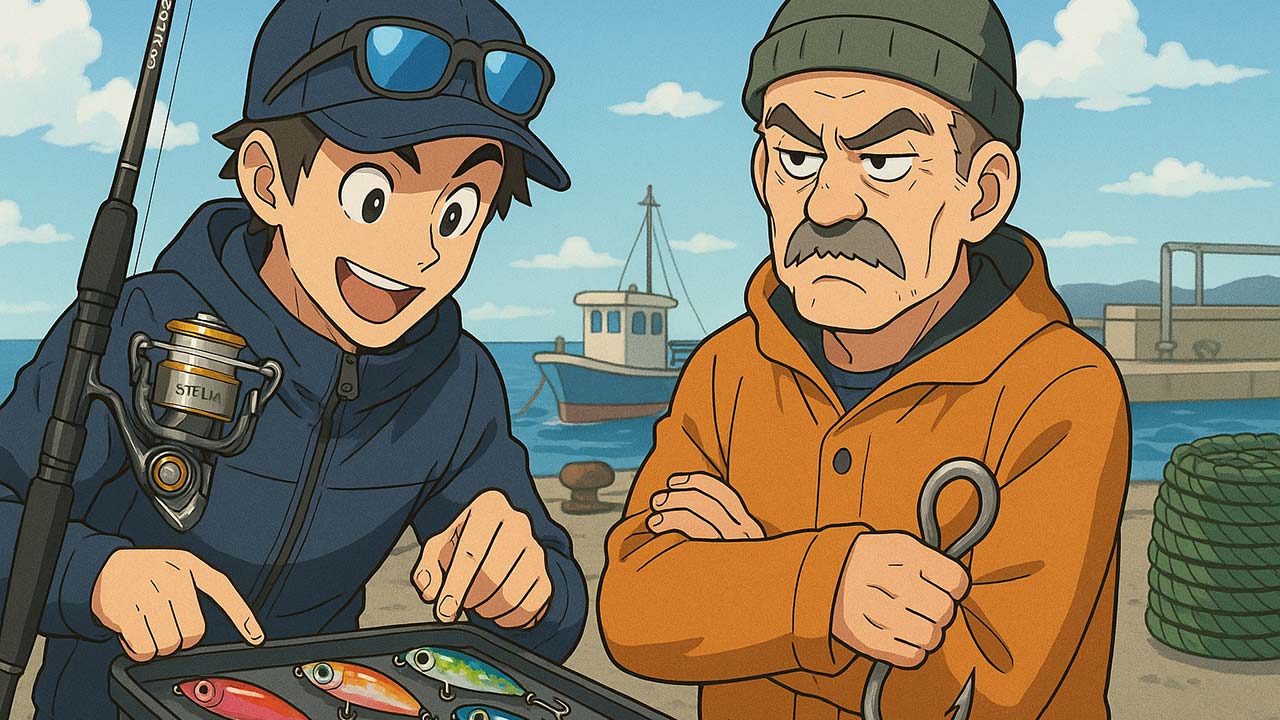はじめに
海に向かう朝は、いつも少しだけ緊張する。
風は穏やかか。潮は動くのか。水温は上がったのか。鳥は舞っているか。
そして今日は、海がどんな顔を見せてくれるのか。
魚を相手にするというのは、ある意味で「自然との対話」そのものだと私は思っている。
この対話に挑むとき、人は大きく2つのアプローチに分かれるように感じる。
- 道具から入る釣り人パターン
- 針から入る漁師パターン
私は幸運にも、その両方の世界に少しずつ身を置かせてもらっている。
趣味としての釣り人。生業としての漁師。
どちらが正しいとか優れているという話ではない。ただ、視点の違いが実に面白いのだ。
今回の記事では、この「魚を獲る2つのパターン」について、私なりの経験と視点を交えながら少し掘り下げてみたいと思う。
道具から入る釣り人パターン 〜自己満足と戦略のはざまで〜
釣り人は、往々にして「道具」から入る。
これは私自身、長年痛感していることでもある。
新しいロッドが発表されると、すぐにスペック表を睨み、曲がり方や反発力を想像する。
リールのギア比や巻き取り長を細かく計算し、ドラグ性能に思いを馳せる。
PEラインの号数とキャパシティを計算し、ナブラまで届く射程距離をシミュレーションする。
そしてルアー。カラー、サイズ、アクション、浮力設計、フックバランス……。
— これらすべては、ある意味で「準備という名の釣り」そのものである。
例えば私が積丹沖で狙うクロマグロ。
準備段階から、タックルセッティングは既に戦いの始まりだ。
オシアプラッガー・フルスロットルを選ぶのか、フレックスドライブを選ぶのか。
ステラSWのスプールはPE6号で臨むのか、PE8号まで上げるのか。それともPE10号か?
リーダーのポンド数をどう組むのか。
これら全てを決めるプロセスそのものが、釣り人にとっての醍醐味となる。
釣り人は「まだ釣っていない魚」をイメージしながら、最適解を組み上げていく。
それは、魚と戦う前に、自分の妄想と戦っているようなものでもある。
極端に言えば——
釣り人は、釣る前から楽しんでいるのだ。
もちろん、これは決して悪いことではない。むしろこの段階が最も濃密な時間でもある。
どれほど魚の反応が悪い日でも、「今日も最高の準備はした」という安心感が心の支えになるのが釣り人なのだ。
針から入る漁師パターン 〜確実性を積み上げる職人〜
一方、漁師は「針」から入る。
魚を獲るという一点に集中し、その核心は「いかに魚を掛けるか」に尽きる。
- 針のサイズは何号がベストか
- ハリスは何号で、どのくらいの長さにするのか
- 幹糸との結束は直結かスナップか
- 餌の付け方、刺し方
- 浮力、沈下速度、潮流に対する角度の管理
漁師の仕掛けには「量産性と確実性」が求められる。
1回のチャンスを逃すかどうかではなく、毎日何十回・何百回と繰り返す作業の中で、いかにミスを減らし、歩留まりを上げていくかがすべてだ。
私も秋には鮭定置網の仕事を手伝わせてもらっているが、そこでもやはりこの「確実性へのこだわり」を肌で感じる。
定置網で鮭が掛かる仕組みは極めて合理的であり、網の編み目の大きさ、沈み方、誘導網の角度までが緻密に計算されている。
魚の習性を徹底的に読み、その上で「勝手に掛かってくれる仕組み」を作り上げていく。
ここにおいては、リールのギア比やロッドのカーボン素材はまったく議題に上がらない。
それでも毎年、圧倒的な成果を上げ続けている。
「釣り」と「漁」はやはり別物なのだと痛感させられる瞬間でもある。
2つの視点を往復して思うこと
私は幸いにも、趣味の釣りと生業の漁の両方に少しずつ関わらせてもらっている。
だからこそ、両者の視点を何度も往復する機会がある。
釣り人は「魚の反応を楽しむ」。
漁師は「魚の習性を支配する」。
釣り人は「道具にこだわる」。
漁師は「仕掛けを合理化する」。
釣り人は「答えのない仮説を繰り返す」。
漁師は「実績のある公式を磨き続ける」。
どちらも魚を相手にしていることは同じでありながら、ここまでアプローチが違うのは実に興味深い。そして面白いことに、両方を経験してもなお、私はいまだに「自分はどちら寄りの人間なのか」わからないでいる。
強いて言えば、両方の良いところを混ぜながら、今も模索している最中なのだろうと思う。
技術的な”境界線”を考える
釣りと漁を分けるもうひとつのポイントは「許容できる失敗回数」かもしれない。
釣り人にとって1回のバラシは「悔しさ」で済む。
だが漁師にとってのバラシは「収入減」になる。
だからこそ釣り人は「攻める道具」を選ぶ余地があり、漁師は「守り切る仕掛け」を作り続ける。
たとえばマグロゲームの世界で言えば、釣り人はPE6号・8号・10号と細かく迷い、漁師はロープの太さと結び目強度に悩む。
どちらも真剣であり、どちらも職人である。
だからこそ、私は両方の現場が好きなのだと思う。
すべては「魚と向き合う時間」が教えてくれる
海に出るたび、釣り座に立つたび、仕掛けを投入するたびに思うことがある。
魚が教えてくれるのは、こちらの準備の質そのものであると。
- 道具を極めたつもりでも外す日もある
- 仕掛けを工夫しても思わぬ潮で沈黙する日もある
- 完璧に組み上げたつもりのラインが、高切れを起こすこともある
そのすべてが、次回の準備へとつながっていく。
魚を釣るというのは、自己検証の連続なのだと痛感させられる。
終わりに
魚を捕るアプローチには、道具から入る釣り人の世界と、針から入る漁師の世界がある。
どちらが優れているかではなく、どちらも魚に敬意を払い、向き合っている姿には違いがない。
私は今日も海へ出る。
そしてまた、釣り座に立ち、仕掛けを沈め、魚がどう答えてくれるのかを待つ。
きっとまた、新しい発見と、少しの失敗と、小さな成功が積み上がっていくはずだ。
釣りとは準備であり、釣行はその答え合わせ。
この言葉を胸に、これからも私は魚たちと対話を続けていきたい。